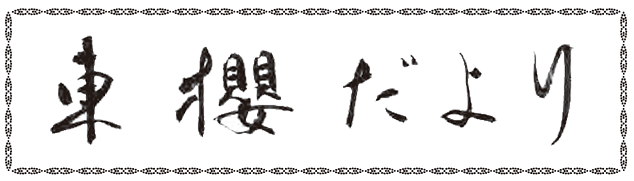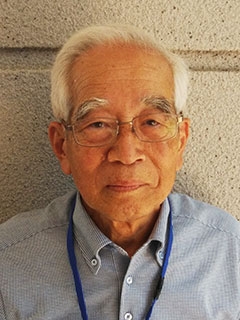附属京都小への思い入れ
元 副校長 迫田 恒夫
私が附属京都小へ赴任したのは昭和42年、30歳の時でした。当時はプールの北側に木造2階建ての校舎がありました。この校舎は私が附属京都中2年のときに建てられたもので、私たちはまっさらの教室で勉学に励んだのですが、年数が経って取り壊す直前、今度は学級担任としてその校舎に入るという巡りあわせに、この校舎との強い因縁を感じました。そのころ今の大運動場は中学校が使用しており、小学校は体育館の西側(今の総合館の西側)の運動場で体育の授業も運動会も行っていました。勿論、今の小運動場よりはかなり広かったのですが、でもよくあのような広さで700人を超える児童が活動できたなあと思います。赴任の翌年、大運動場が小学校所管になって、やっと羽を伸ばせた思いでした。
私が副校長を拝命した年は悪天候に振り回されました。大雨警報下の運動会、研究発表会には台風の襲来、とどめは入学検定の大雪。一時検定(抽選)で遅刻された保護者を締め出したことで大騒ぎになり、マスコミ応対に大汗をかきました。
次の年が附属京都小学校の創立100周年の年でした。それまで正面玄関は車寄せになっていて、普段は使われていない開かずの扉でした。子どもたちは東・北昇降口から登校していました。私は学校の主人公である子どもたちを正面玄関から迎え入れたいという強い気持ちを持っていましたので、同窓会や育友会にも大々的な募金をお願いし、おかげさまで現在のような景観が生まれました。大変な工事でしたが、子どもたちの正面玄関からの登校を実現することができ、何よりでした。
100周年の年に開催された同窓会総会・記念祝賀会には500人を超える同窓生が参加され大盛会となりましたが、これを機に同窓会活動を活発化させようということで、人生の折り返し点である40歳(その頃はまだ人生80年という言葉が生きていた)になれば同窓会活動の当番役(総会の世話・機関紙の発行など)をしてもらおうということになり、爾来その営みが続けられてきました。
それから数年経って、私たちの長年の夢であった体育館の建て替え、ランチルーム(現在の総合館)の新築が認められました。体育館はミニバスケットボールコートを3面確保する、階段いすも準備し全校児童が集まっての式典や学芸会もできるようにと、いろいろアイデアを練ったものです。現在、体育館の北入り口は幅広い階段状になっていますが、大学施設課から最初提示されたのは「西側にごく普通の入り口」でした。将来本館工事の際にはここが学校の顔になるところだからもっといいプランをと強く要望し、何回ものやり取りの末1学年の児童が座って話を聞くことができる階段式の現在の形にもっていくことができました。初志貫徹と言いましょうか、粘り強く取り組むことの大切さを学びました。
正面玄関の工事の間、中庭の通路は通行禁止となり、子どもたちに不自由な思いをさせましたので、工事が終わってから通路部分に人工芝を敷くことにしました。敷いて間なしでした。ふと中庭に目をやると、長い通路に子どもがびっしり座り込んで嬉々としておしゃべりしたり、手遊びしたりして遊んでいるではありませんか!私はその光景が忘れられません。
長い副校長生活の間には、大雪の入試のような辛いこともありましたが、人工芝の上で遊ぶ子供の姿に心を打たれるようなことも多々ありました。附属京都小学校に思い出は尽きません。ありがとうございました。末筆ながら、100周年・山の家・校舎改築等に際して協力いただいた方々、本当にありがとうございました! 紙面をお借りして厚くお礼申し上げます。