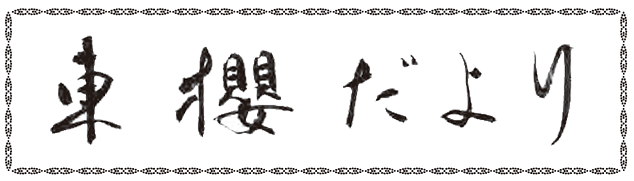タイ国生徒相互訪問交流事業に寄せて
前 副校長 垂井 由博
目に涙をいっぱい浮かべてタイ国の生徒たちは帰国の途につきました。
京都駅での見送り。たくさんの本校生徒やホストファミリーに見送られて別れを惜しみました。たった1週間、ホストファミリーには3日間だったのに、なぜこんなに涙が溢れてくるのでしょう。もう一生会えないかもしれない…。いや、きっとまた…。でもいつか再会がかなったとしても、もうこんな形のものではないでしょう。お互いにそんな思いが胸にこみあげ、時間がここで止まってくれたらと誰もが願ったに違いありません。
発車寸前までドアが開かず、車内の窓際から別れを惜しむ十分な余裕も与えないまま、すぐにスピードをあげてゆく「はるか」。その快適さとは裏腹に、別れを惜しむ者にとってこの近代的な列車はあまりにも無情でした。ホームの人影が流れるようにあっという間に目の前を通り過ぎ、その人影が見えなくなる最後の最後まで窓に顔をすり寄せ、途方もなく大きな駅ビルが本当に小さくなって見えなくなるまで、タイ国の生徒たちは決して窓際を離れようとはしませんでした。
関西空港での見送りは、私1人の特権となりました。みんなの思いを代表して、彼らの帰国を見送りました。日本での体験をいっぱい詰め込んで、来日したときよりもずっと大きな荷物を抱えていました。ある生徒は、たぶん中に入り切らなかったのでしょう、生徒交流会でもらったヨーヨーをいくつも手に持っていました。縁日の祭りで見かけるようなヨーヨーつりのヨーヨーも、彼女にとっては心を通わせた大切な思い出の品なのです。大きな荷物を運ぶのに邪魔になって立ち往生しても、まだ大切に手に持っていました。
そして、タイ国の生徒たちは1列になって国際線出発ゲートを入っていきました。ここから見送りの者はもう立ち入ることができません。帰国を見送る最後の場面です。ゲートの遠く後方に仕切られた壁の奥に消えるまで、タイ国の生徒たちは振り返り、振り返り、さようならの手を振ってくれました。列の最後尾にいたスワット先生は、一旦壁の奥に姿を消してからまた戻り、私がまだ帰らずにいることを確認すると、両手を大きくあげて振り、これを3回繰り返して去っていかれました。その姿が今でもまだ目に焼きついて、離れないのです。―――――
1997年に始まった、附属京都小中とタイ国アユタヤ大学附属中等教育学校との交流開始当初のエピソードの一節です。スワット先生はこの後学校長になられ、長年、本交流事業の立役者として貢献されましたが、コロナ禍となる直前に定年退職されました。
同窓会からも多大なるご支援を得ながら25年余りにわたって継続してきた本交流行事は両国の中学生に大きな心の成長を与えてきましたが、コロナ禍中の3年間は相互訪問交流も中止を余儀なくされ、その再開を待たずに私も定年退職を迎えることとなりました。
本行事は私の教員時代の大きな思い出の一つです。定年退職直後、まずしたことはタイ国への個人的突撃訪問。スワット先生にも4年振りに再会でき、25年余りにわたる交流活動の苦労と思い出話に花を咲かせました。定年退職した2人ですが、両国の生徒の成長に寄与してきた本交流の再開と継続を願い合いました。
そして、コロナ禍も明けた昨年度は、元通りの交流を再開したと聞いています。本行事の意義が確実に次世代に受け継がれていることを大変嬉しく思うばかりです。