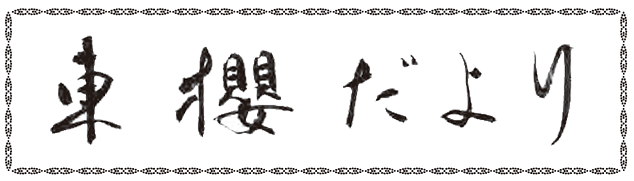同窓会副会長 鈴木 順也
東櫻同窓会のみなさまにおかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、私は昨年7月に開催された小中学校同窓生の集いに出席しました。コロナ感染症による延期などにより、実に6年ぶりの開催でした。出席して驚いたことは、どの方も年齢を重ねられているのは当然ですが、実に幅広い世代・年代の同窓生が集まられたことです。タップダンサーとして活躍され東京2020オリンピック競技大会の開会式に出演した谷口翔有子さんのパフォーマンスがあり、多様な分野に同窓生が進出し活躍していることが心に残りました。しかし、出席者数は多くないという印象を受けました。
東櫻同窓会は今後の運営の大きな岐路に立っているように感じます。長らく副校長を務めてこられた垂井由博先輩が定年退官されました。また、長い習慣により、学年ごとに持ち回りで集いの実行委員を担うことになっておりますが、役割を引き受ける人が出にくい状況が続いていると聞きます。
同窓会員の名簿の更新は、最新の消息が不明の方が非常に多く、もはや会報や集いの案内状を幅広く発送することは難しいということです。中西秀彦常任理事長をはじめとする常任理事の方々のご尽力でようやく成り立っているものの、持続可能な方法とは言いがたいです。
物事のデジタル化が進展する現代社会において、会報をオンライン化し、連絡先の更新は個人の希望と判断によりWEB経由でデータベースを更新するよう、同窓会事務の省力化に舵を切ることは可能です。
しかし、根源的には社会の価値観が多様化するなか、昔のよき学生時代を懐かしむという文脈における同窓会のあり方の変化と見直しの時期に来ているのではないでしょうか。母校や友人に対しての想いは、人それぞれ多様であると考えられ、早急に結論を出すことはできませんが、私はあえて問題提起させていただきたいと思いました。